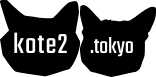- kote2.tokyo
- >
- Blog
- >
- 「ウェブはグループで進化する」を読んだ
「ウェブはグループで進化する」を読んだ
- Update2012-08-13
- Category
- Design/UI/UX
- Other--
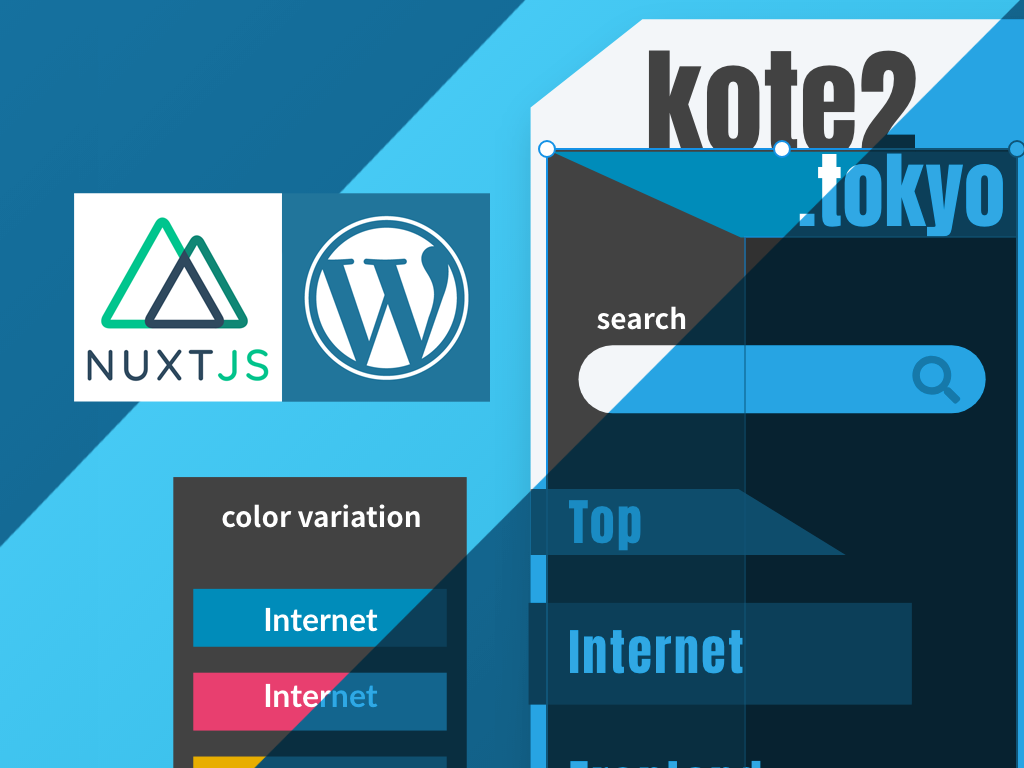
Google+やFacebookの開発に携わり、またダイソンの掃除機のプロダクトデザインにも携わったことのあるポール・アダムス著の「ウェブはグループで進化する」を読んだ。
Googleのグループ機能(サークル)のデザイン設計の基礎を作ったのが著者との事だが、この本を執筆した時にGoogleから出版中止を要請され、競合のFacebookに移籍、内容をもう一度書きなおして出版したとのことで、Googleのサークルの概念が、出版中止となった本とかなり被っているとの事で曰くつきの本です。というわけで興味が湧いて買ってみた。
目次
第1章 変化するウェブ
第2章 人々がコミュニケーションをとる理由と方法
第3章 ソーシャルネットワークの構造が与える影響
第4章 人間関係が与える影響
第5章 インフルエンサーという神話
第6章 周囲の環境が与える影響
第7章 脳が与える影響
第8章 先入観が与える影響
第9章 ソーシャルウェブにおけるマーケティングと広告
第10章 結論
第1章の「変化するウェブ」では、ネット上の大量の情報にアクセス可能になった事による人々の情報の探し方、あるいは捉え方の変化の推移が書かれており、一方的なコンテンツ型から人中心型へ変化している様を背景に、今までのネットビジネス、特にプロモーション面においては考え直す必要があると警鐘。以降の章からひとうひとつ丁寧に、自身がFacebookに勤めてることもあり説得力のあるデータも加え解説している。
人間が意思決定する時の脳は、無意識で決断を下す部分が70%を占めており、この行動、あるいは本能を見逃してはならないと唱っている。その本能が実証され得るのは、現代のSNS、FacebookやGoogle+など、友人同士のつながり、グループの存在で、人々の興味そして意思決定は、環境が密接に絡んでいる事を分析できるようになったからだと。
無意識に訴えかける情報とは、人間の脳本来の働きに基づいたものであり、それは感情に関するものや、見栄、他人を助けたい気持ち、など、どういう内容が一般に話題になるのか、また話題に関しても、オフラインとオンラインの違いなどが明らかにされている。この章は面白いのでおすすめです。(第7章 脳が与える影響、第8章 先入観が与える影響)
第9章の「ソーシャルウェブにおけるマーケティングと広告」では、テレビCMなどの一方的な広告手法を妨害型マーケティング、Facebookなど、一旦許可(いいねしたら情報が流れる)したら情報が入るようになうやり方を許可型(パーミッション)マーケティングと称し、人々に企業メッセージがリーチする比較をしている。よく言われるのが何十回のCMより友人家族の一言が意思を決定づけるなんて言うけど、それを数字と事例で解説。大部分の人々はもう企業マーケティングを信用しておらず、本当のファンだけにプロモーションすべきである、つまりいいねしてくれた許可型マーケティングを推し進めるのが今後の人中心型のウェブで基本になってくると。
最終的に、じゃあ今後のビジネスはどうなるのかというのを書いてはいるが、その中身はほとんど今まで語ってきた内容のまとめみたいなもので、「もうみんなわかってるよね?」というような感じでページ数も最終章は少ない。人中心型のウェブを理解するには人そのものを研究(社会行動、ネットワーク構造、思考回路等)し、新しい知識体系が求められてるとの事です。これはマーケターだけでなく、ウェブに携わるものならすべての人に必要なテーマと閉めくくっていました。
あっという間に一冊読み終えた時に、なんかものすごく勉強した気持ちになる一冊でした。いや、気持ちや視点はこの著者が書いてあることに自分も全く同意だけど、こうやって心理学とか人間行動学、現状のSNSのデータでしっかり解説してくれてるのでとてもためになる本です。定期的に反復して読むべき本だね。